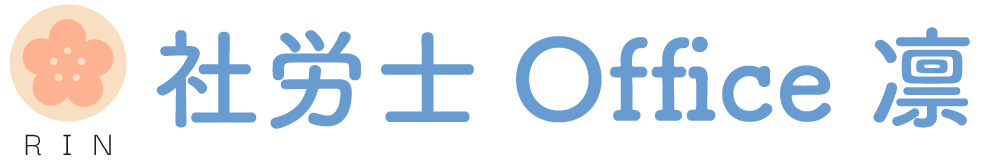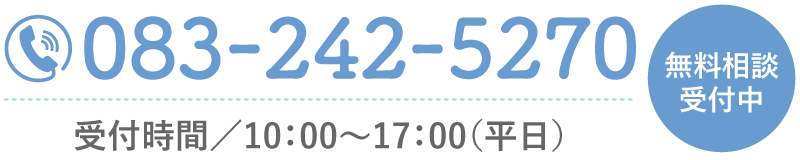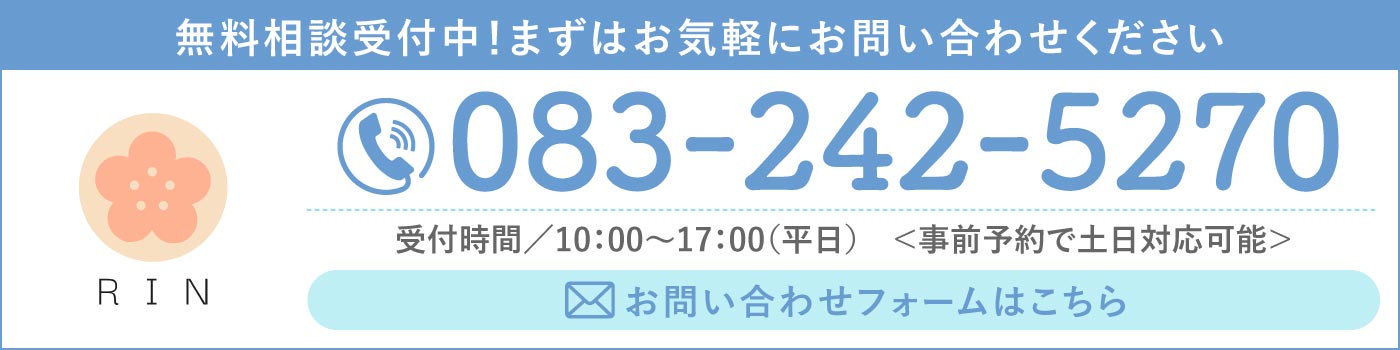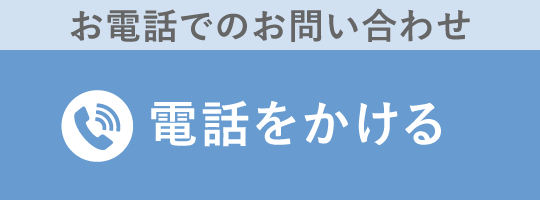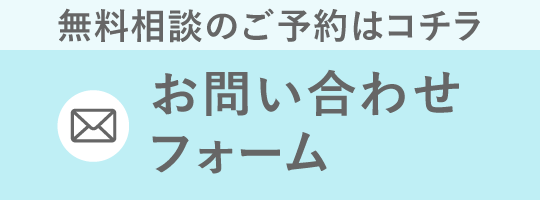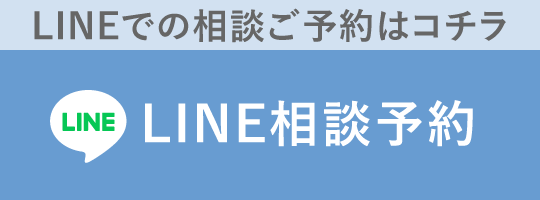こんにちは。
山口県下関市の社労士Office 凛です。
このページの目次
一般的な診断書と障害年金の診断書の違い
日頃病院でもらう診断書と、障害年金を申請するときに必要な診断書。
どちらも“診断書”という名前ですが、書かれている内容はけっこう異なります。
たとえば精神科で休職や保険会社への提出のために作成される「一般の診断書」には、次のような内容が記されます:
- 診断名(うつ病、双極性障害など)
- 現在の症状(抑うつ、不安、不眠など)
- 通院や治療の経過
- 就労の可否など
これらは主に「医学的な状態」を示すものです。
一方で、障害年金に使う診断書では、日常生活にどの程度支障が出ているかが重視されます。
日常生活の困りごとを具体的に書く
障害年金の診断書では、「精神の障害用」の場合、次のような生活面の評価が必要です。
- 食事や着替えなど、身の回りのことが自分でできるか
- お金の管理や買い物ができるか
- 薬の管理、通院ができているか
- 人との意思疎通ができるか
- 判断力や安全への配慮があるか など
これらは等級判定に直結する項目であり、医師が適切に記入できるよう、事前に生活の実情を伝えることが非常に重要です。
医師に伝えるときの工夫(ただし、配慮も大切)
障害年金の診断書では、日常生活でどれだけ困っているかを正確に伝えることが大切です。
そのため、診断書をお願いする際に
- 医師向けの説明資料(記入例など)を添える
- ご本人の生活の様子を簡単にまとめたメモを用意する
といった工夫が、内容の充実や医師の理解につながることがあります。
ただし、こうした資料の提出を好まない医師もいらっしゃるため、必ずしも「渡すことが正解」とは限りません。
そのため、
こうした対応をするかどうか自体も含めて、相手の先生のスタンスを見ながら慎重に判断することが大切です。
渡す場合でも、
「診断書をお願いしたく、生活の様子を簡単にまとめたものをお渡ししてもよろしいでしょうか?」
と一言確認してから渡すのが望ましい対応です。
まとめ 出す前の確認がカギです
診断書は、一度出してしまうと訂正が難しい書類です。
だからこそ、出す前の準備や確認がとても大切です。
「このまま出して大丈夫か不安…」という場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は、全国対応の社会保険労務士事務所として、障害年金の申請サポートおよび労務顧問を専門に行っております。
年金事務所での相談業務経験を持つ社会保険労務士とスタッフが、診断書の取得から申請書類の作成・提出までをトータルサポートし、一人ひとりの不安に寄り添い、丁寧に支援いたします。
「まずは話だけでも聞いてみたい」という方のために、初回相談は無料で承っております。また、遠方の方でも気軽にご相談いただけるよう、全国対応のオンライン相談も実施しております。
お困りのことがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。